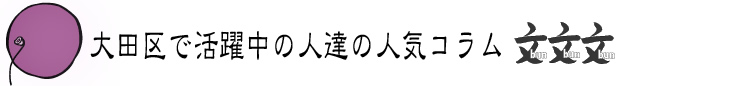章子の一葉記 上 ―のぼせ性― 澤田章子

大田区在住の様々なジャンルで活躍中の方々にいろいろな文を書いていただくコラム、スタート。トップバッターは上池台の文芸評論家澤田章子さん。秋には五千円札に登場する樋口一葉の研究家だ。
2004年4月掲載
「おおかた逆上性(のぼせしょう)なのでござんしょう」とは、「にごりえ」の主人公お力の言葉だが、樋口一葉も自分をのぼせ性と思っていたに違いない。
十九歳で小説をこころざした一葉が、『東京朝日新聞』の小説記者だった半井桃水(なからいとうすい)に弟子入りするため、初めて訪れた時の日記を読むと、一目惚れだったことがよくわかる。「誠に三才の童子もなつくこそ覚ゆれ」と、その第一印象のよさが書き表わされているのだ。
その桃水への恋は、しだいに熱を帯びたものになっていったが、けっきょくは片思いに終わっている。桃水は一葉を作家にしようと親身に尽くしたが、十二歳違いの一葉を妹のように見ていたようだ。一葉も後には、「誠の兄君伯父君などのやうにおぼゆ」と書いて心の決着をつけている。
桃水との距離ができてからは、『文学界』の同人である若い文学者が訪れるようになる。
馬場孤蝶(こちょう)は自由民権運動の闘士辰猪(たつい)の弟で、二歳上の二十五歳。穏やかな桃水に比べると、血気盛んな若武者のような人物だった。「慷慨非哥(こうがいひか)の士なるよし語々癖あり不平不平のことばを聞く、うれしき人也」と共鳴を示している。
文壇ですでに名を馳せていた川上眉山(びざん)が孤蝶に導かれて一葉に会いに来たのは、それから一年あまり後のこと。「孤蝶子のうるはしきを秋の月にたとへば眉山君は春の花なるべし」と、その美男ぶりをたたえ、つい十日前には金のないことを嘆いて「かしら痛きことさま 多かれど」と書いたにもかかわらず、鰻を取り寄せてご馳走している。
一葉はついに結婚もせず、二十四歳で生涯を閉じたが、貧しく、苦労の多かった生活に豊かな文学的滋養を注いだのは、これら男性作家たちであった。一葉の日記を世に出すために力を尽くしたのも馬場孤蝶である。
(さわだあきこ)