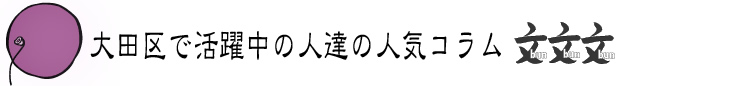喪中の哲学 東雲 哲哉
2008年1月掲載
こっちが年を取るから、友人から来る喪中はがきが年々増える。今年も早々と十二通が来た。多くは親についてのものだが、その長寿ぶりに驚く。十二通のうち年齢を書いていないのが三通あったが、残り九通のうち七通が九十歳以上だった。二通の一人も八十八歳で、六十三歳という人が飛び離れて若かった。
先ごろ厚労省から発表された日本人の平均寿命が、男が七十九歳、女が八十五歳だから、「八十、九十は当たり前、七十代だと早過ぎる」といえ、驚くにあたらないのかも知れない。
昔の会社仲間でゴルフコンペをやっていて、その会を「きんざら会」という。数年前、ある人の「古稀」を記念してやり始めたのだが、「昔は古来稀と言った七十歳も、近年ざらだ」というので、そう命名した。いまや六十五歳の私が若手の方で、七十台がぞろぞろいる。ぞろぞろと九十になるのか。
ある新聞のコラムで、最近の自分の気分として、「門松は冥途の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」という一休の歌を引いていた。しかし、私にはちょっとピンとこない感慨だといえる。
時の流れがやたら早く、めでたいとか感じている暇がないのだ。長寿の時代のせいではないか。時間が一年単位で流れているというより、数年単位で飛んでいる感じがある。
だとすれば、一年が人間の四年分に相当するというネコと同じになったということだ。
あっという間に、八十、九十になる。八十、九十になっても、肉体の変化はともかく、心の中では四、五年しかたっていない感じということだ。衰えの目立ってきた十七歳のわが家の長男ネコと、気分的に同じということでもある。
彼には腎臓機能を維持するために、毎日点滴をしていて、私は動かないように前足を押さえる役目だ。その時、目と目を見つめ合いながら、お前は何を考えていると、問うているのだが、彼もこっちに「ご同輩、何を考えているの」と問いかけているのだろう。
●東雲 哲哉(しののめ てつや)
下丸子在住
元新聞記者